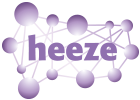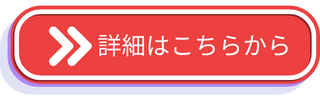ミセルチカラの磨き方
数字も正しい、でも伝わらない─感情を「事実」として扱う経営者の対話術
ヒーズ株式会社の岩井徹朗です。
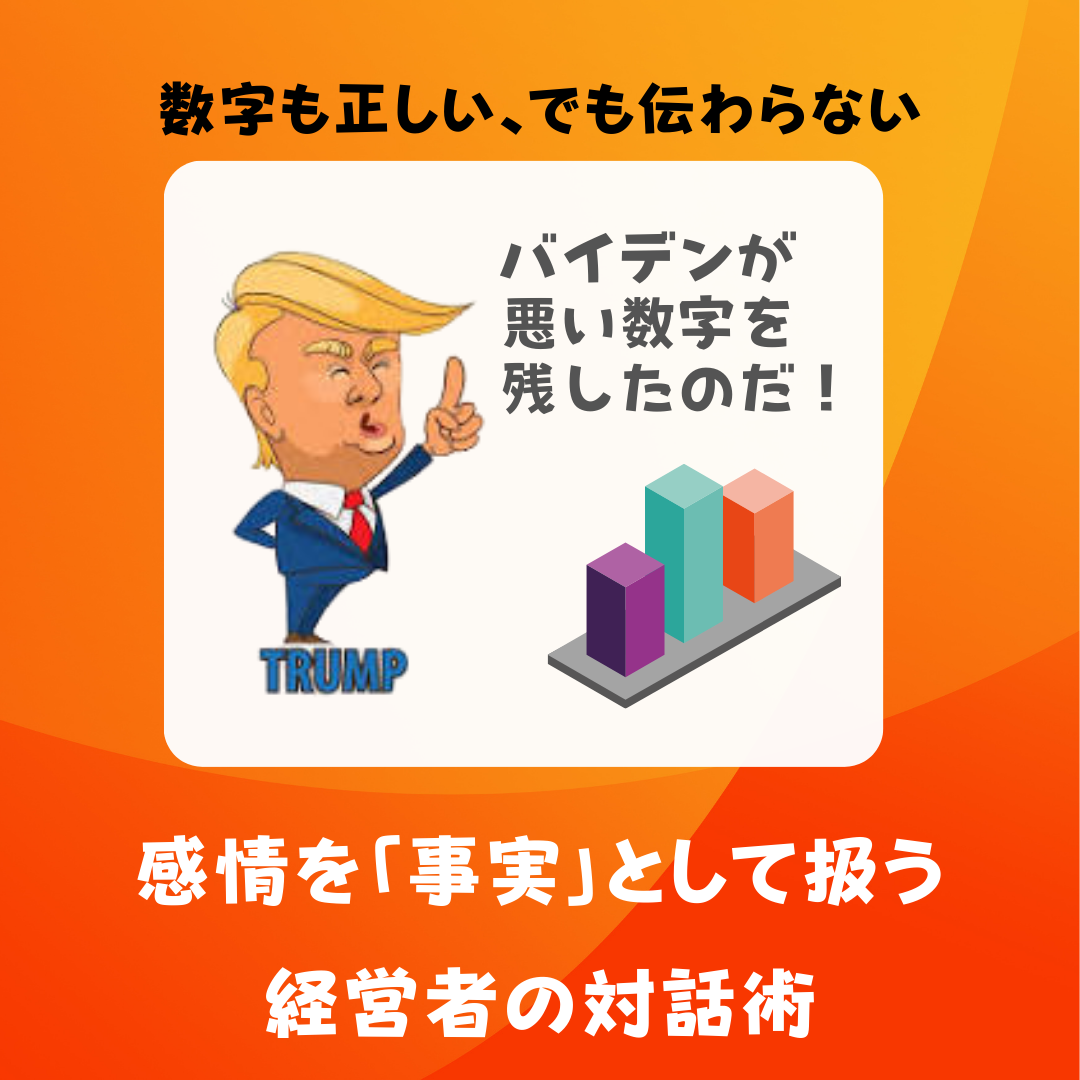
「バイデンが悪い数字を残したのだ」
アメリカの1月から3月までの実質GDP(国内総生産)の伸び率は、年率換算で0.3%減と、3年ぶりのマイナス成長になったことを受けてのトランプ大統領の発言です。
皆さんはどのように感じたでしょうか?
多くのニュースではトランプ政権の関税対策を景気後退と結びつける内容が多い中、悪いのは自分ではないという主張です。
石破首相が「岸田前首相の政策が悪かった」と発言すれば、日本では大騒ぎになりそうですね。
日本の場合は、他者に責任を転嫁するような姿勢は潔いとは思われません。「男は黙って」というフレーズが昔流行ったように、言いたいことは心の奥底に秘めて、自分のやるべきことを愚直に取り組むことを良しとする考え方からすれば、「また、あのトランプが」と眉をひそめる人も多いのではないでしょうか。
人は他者の言動を感情を伴って受け取ります。その言動が事実として正しいかどうかは別にして、「その通りだ!」と共感する場合もあれば、「そりゃおかしいでしょ!!」と反発する場合もあります。
「事実」とそれに伴う「解釈」がセットになると、その人にとっての「真実」になります。そして、「解釈」の部分については、その人の価値観なり、思惑なりが反映されるので、1つの「事実」に対して、無数の「真実」があります。
このため、問題解決につなげるには相手の解釈が入った「真実」に振り回されるのではなく、まずは「事実」関係を明らかにすること。
そして、「事実」を明らかにした後で、相手の解釈の背景にある価値観や思惑に思いを馳せることです。
前述のアメリカのGDPに関して言えば、数字の分析をすれば、必ず事実にたどり着きます。おそらくバイデン前大統領時代の政策による影響もあれば、トランプ大統領の政策による影響も少なからずあるはずです。
ただ、「事実」関係を明らかにしたところで、相手が過去の主張をすぐに変えるかどうかは別問題。特に一定の力を持った人の場合、意図的に自分にとって都合の良い事実だけを強調する傾向があるからです。
会社経営においても、特にオーナー経営者は「自分は悪くない」と主張しがちです。それに対して、事実を基にして行動変容を促すのは簡単ではありません。
弊社で「感情→思考→行動」によるアプローチを始めたのは、定例の打合せで「これをやりましょう」といったん合意したことが、翌月になって「やってません」というケースがいくつか出てきたことがきっかけです。
例えば、数字をベースに会社の実態を分析し、「今月は粗利の改善に力を入れましょう」と決めたのに、一向に進んでいないことがありました。
その際、「なぜ、やらなかったのか?」と質問しても、「忙しかった」とか「新規の受注に時間を取られていた」といった回答が来るばかりで、改善にはつながりません。
粗利の改善は地道な仕事です。また、いま取り組んだからといって、すぐに劇的な効果が出るとは限りません。しかしながら、早めにかつ愚直に取り組むことが確実に業績改善につながる仕事です。
このため、事実を基に説得しても、経営者が真に腹落ちしないと、「やっぱりまじめにやろう」とはなりません。
その際、
- 行動のベースとなる思考の癖
- 思考の癖の背景にある感情の動き
に着目することで、相手に対して「どのような言葉で伝えると、『なるほど!』と思ってもらえるか」が徐々に分かってきました。
つまり、「事実」を共有するだけでなく、「思考」の癖や「感情」の動きを共有することで、お互いのコミュニケーションがよりスムーズになったという訳です。
そして、その際のポイントは、相手の「思考」や「感情」に必ずしも共感する必要はないということ。
人は生まれ育った環境やどのような教育を受けてきたかによって、感情や思考が育まれます。そのため、他人がその人の感情や思考に思いを馳せることはできても、100%理解することはしょせん無理な話です。
しかしながら、相手が「こういうところに感情が動くのか」「この行動の背景にはこのような思考が働いているのか」という「事実」が分かると、相手の言動に必要以上に振り回されることが確実に減ります。
相手の感情や思考を事実としてリスペクト(尊重)しないと、話し合いは上手くいきません。なぜなら、人は「この人は自分をバカにしている」と感じたら、せっかく相手のためと思って練りに練った提案も聞く耳を持たなくなるからです。
数字などで表現される「勘定」としての「事実」と、その人の価値観を形成する「感情」としての「事実」が明らかになれば、問題解決への道筋が見えてきます。
★自分の価値観を形成する事実を明らかにして、仕事に活かしたい方は「こちら」がお役に立ちます。
↓ ↓ ↓
★関連する記事は
↓ ↓ ↓
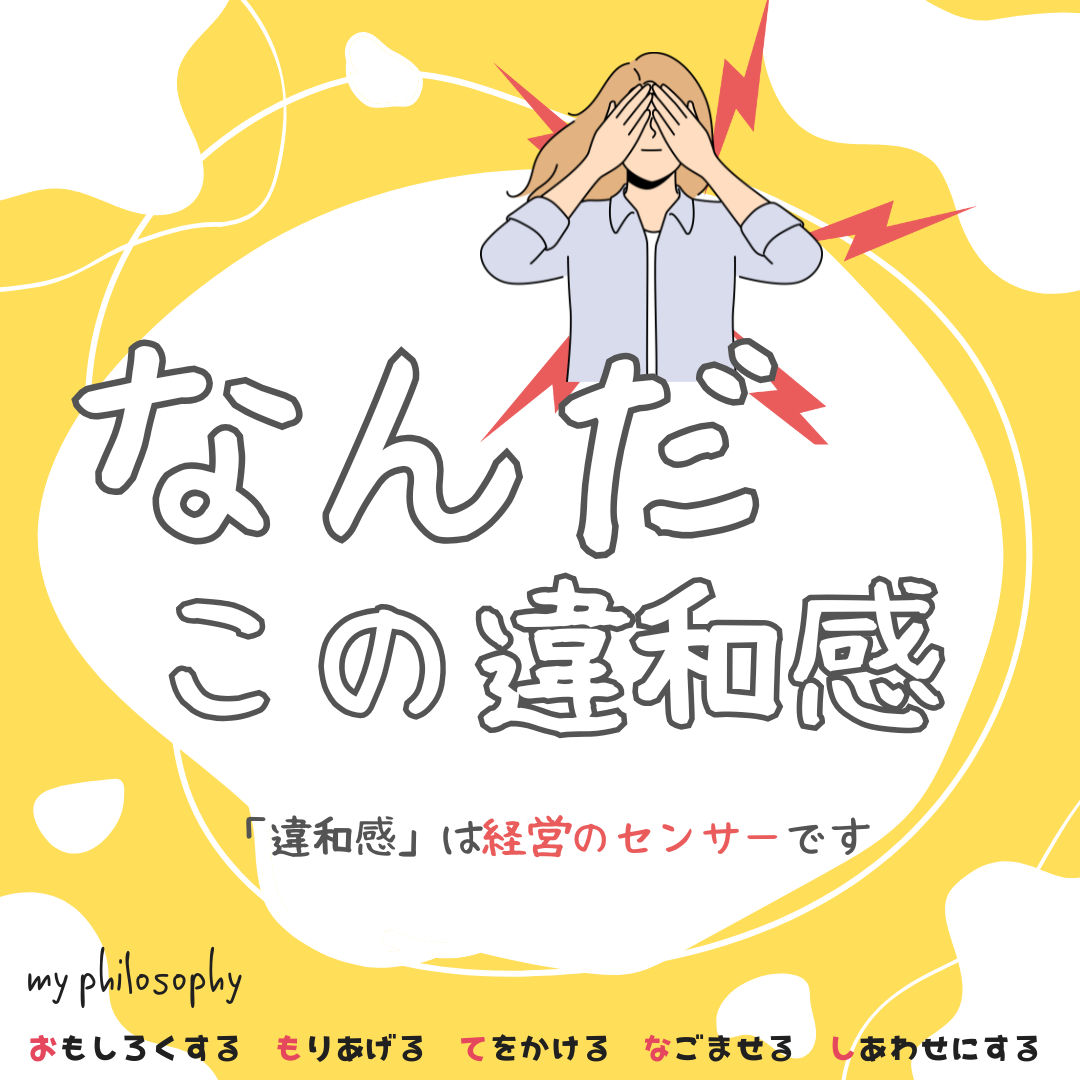
「ちょっとした違和感」を意識的に感じることで、自分の価値観と直結することにたどり着きます。そして、経営判断を支えることになるのは、「静かな違和感を聴きとる力」です。
ヒーズでは、弊社の日頃の活動内容や基本的な考え方をご理解いただくために、専門コラム「知恵の和ノート」を毎週1回更新しており、その内容等を無料メールマガジンとして、お届けしています。
上記のフォームにご登録いただければ、最新発行分より弊社のメールマガジンをお送りさせていただきます。お気軽にご登録いただければ幸いです。