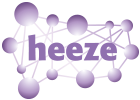ミセルチカラの磨き方
制度は導入して終わりじゃない―サンクスカードに学ぶ「仕組みの育て方」
ヒーズ株式会社の岩井徹朗です。
何か手伝ってもらったり、仕事でサポートしてもらったりした際、感謝の意思を表すツールとして「サンクスカード」を社内で導入している会社もあるかと思います。
社内のコミュニケーションを活性化したり、組織の一体感を醸成したりするための仕組みとして、弊社でもクライアントさんにお勧めすることがあります。
先日既にサンクスカードを導入されている会社の経営者から
「サンクスカードをやっているのですが、総務部ばかりポイントが貯まるんですよ」
というお話をお伺いしました。
サンクスカードを導入する際、
・もらった人にポイントを付与する
・出した人にもポイントを付与する
・半年間など一定の期間で区切って、ポイントの多い人を表彰する
といった制度を設けるのが一般的です。
そして、前述の会社の場合、「サンクスカードをもらうのは総務部の人が多い」という事象が発生していました。
そのこと自体は特に悪いことではありません。しかしながら、経営者からすると
・総務部は基本的には社員のために仕事をする部署である
・このため、「自分のために何かをしてもらった」という点に絞れば、例えば、「総務の人が必要な備品を買ってくれた」というのは、よくある話である
・一方、サンクスカードを出す側がそのような事項にばかり集中してしまうのは本来の主旨や目的が上手く伝わっていない恐れがある
という訳です。
皆さんはどのように思われるでしょうか。
私もかつて総務部に所属していたことがあります。面倒くさいことや、担当部署がハッキリ決まっていない仕事は総務部が担当する、といった企業文化であったこともあり、頑張って何かやったとしても、「ありがとう」と言われたことは少なかった記憶があります(苦笑)。
そういう意味からすれば、サンクスカードという目に見える形で、社員の感謝の気持ちが相手に伝わることはたいへん素晴らしいなぁと感じます。しかしながら、経営者という立場に立つと、サンクスカードをもらうのが総務部に集中している状況は
・同じ部署の上司、同僚や部下の仕事に関心が薄いのではないか
・社員が自分の目標に集中するあまり、周囲との連携や助け合いが少ないのではないか
・自分が(人から)やってもらうことにしか興味がないのではないか
という懸念が生まれてきます。
人は当たり前のことには感謝の気持ちが生まれません。この点、前述の会社ではサンクスカードの導入によって、少なくとも営業など他の部署が総務部に感謝する姿勢が可視化されたのは大きな一歩です。
そして、そこからさらに一歩踏み込んで
自分が直接何かをしてもらった訳ではないけれど、人が会社のためや他の社員のために行っている行動に気づけるかどうか
が次のステージに上がるための試金石になります。
人はどうしても欠点や失敗に目が行きます。そして、その欠点や失敗によって、余計な仕事が増えたり、残業せざるを得なくなったりすると、「アイツのせいで」という思いが募ります。
けれども、何気なくやってくれたり、ちょっとした気遣いのお陰で、余計な仕事が減ったり、上手く仕事が回ったりしても、「あの人のお陰で」とはなかなかなりません。
もし、サンクスカードを導入されていない会社であれば、一度導入を検討してみましょう。また、既に導入されている会社であれば、単にポイントの多い人を表彰するだけでなく、「Aさんはこういったことをやってくれました」「そのAさんの行動にBさんが気づいてカードを書いてくれました」というように、社員に新たな気づきを与えるような発表やコメントを加えてみましょう。
サンクスカードもそうですが、仕組みは創意工夫を重ねる中で磨かれ、進化していきます。
★関連する記事は
↓ ↓ ↓
業務改善がうまくいかない理由はコレ!形骸化した制度を立て直す
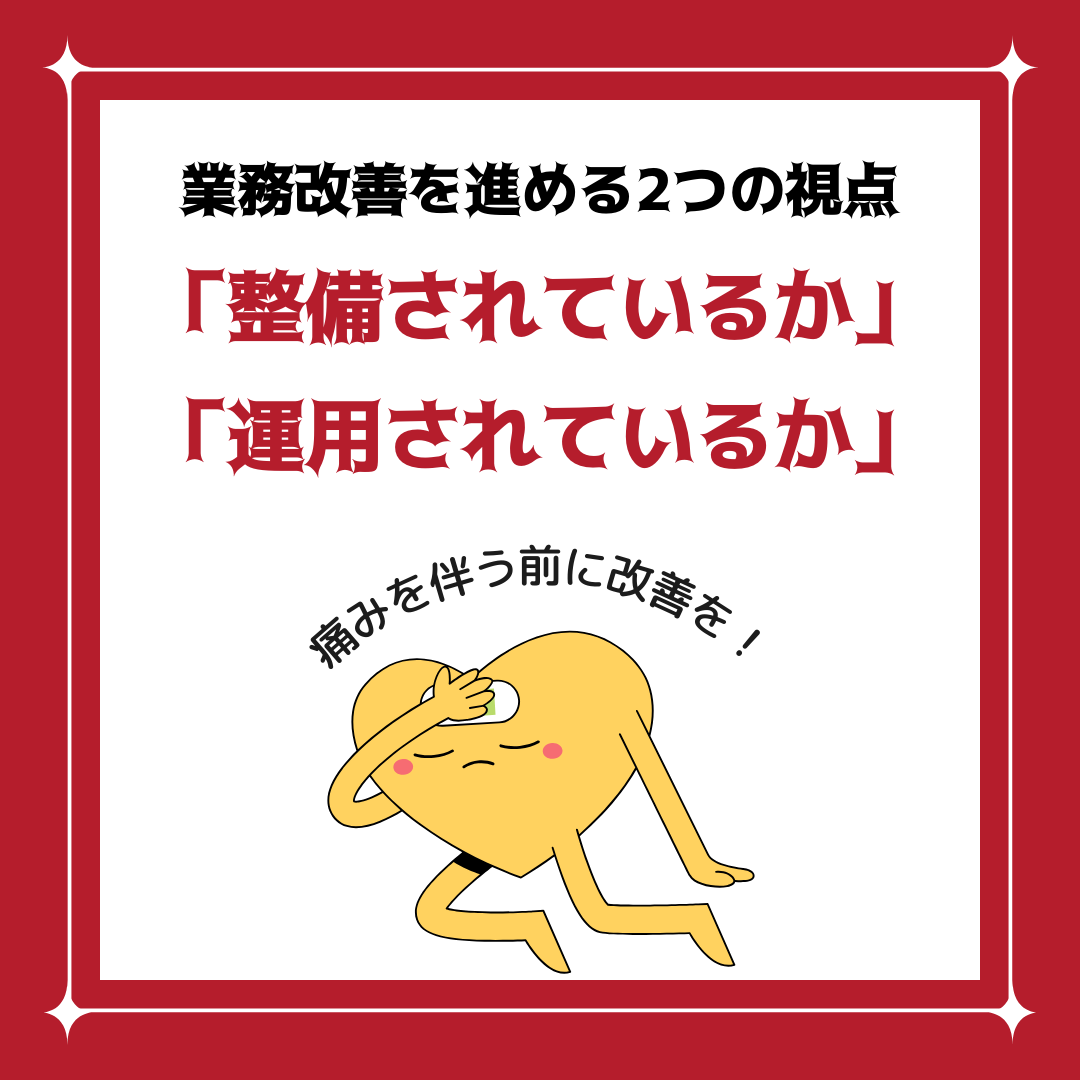
どの業務も、何のためにあるのかを改めて考え、「整備されているだけ」で満足せず、「運用されているかどうか」を問い続ける。これが企業の持続的な成長につながります。
ヒーズでは、弊社の日頃の活動内容や基本的な考え方をご理解いただくために、専門コラム「知恵の和ノート」を毎週1回更新しており、その内容等を無料メールマガジンとして、お届けしています。
上記のフォームにご登録いただければ、最新発行分より弊社のメールマガジンをお送りさせていただきます。お気軽にご登録いただければ幸いです。