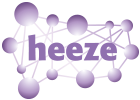ミセルチカラの磨き方
過去の経営判断を未来に活かす:事実と解釈を分けて「学べる記録」に変える方法
ヒーズ株式会社の岩井徹朗です。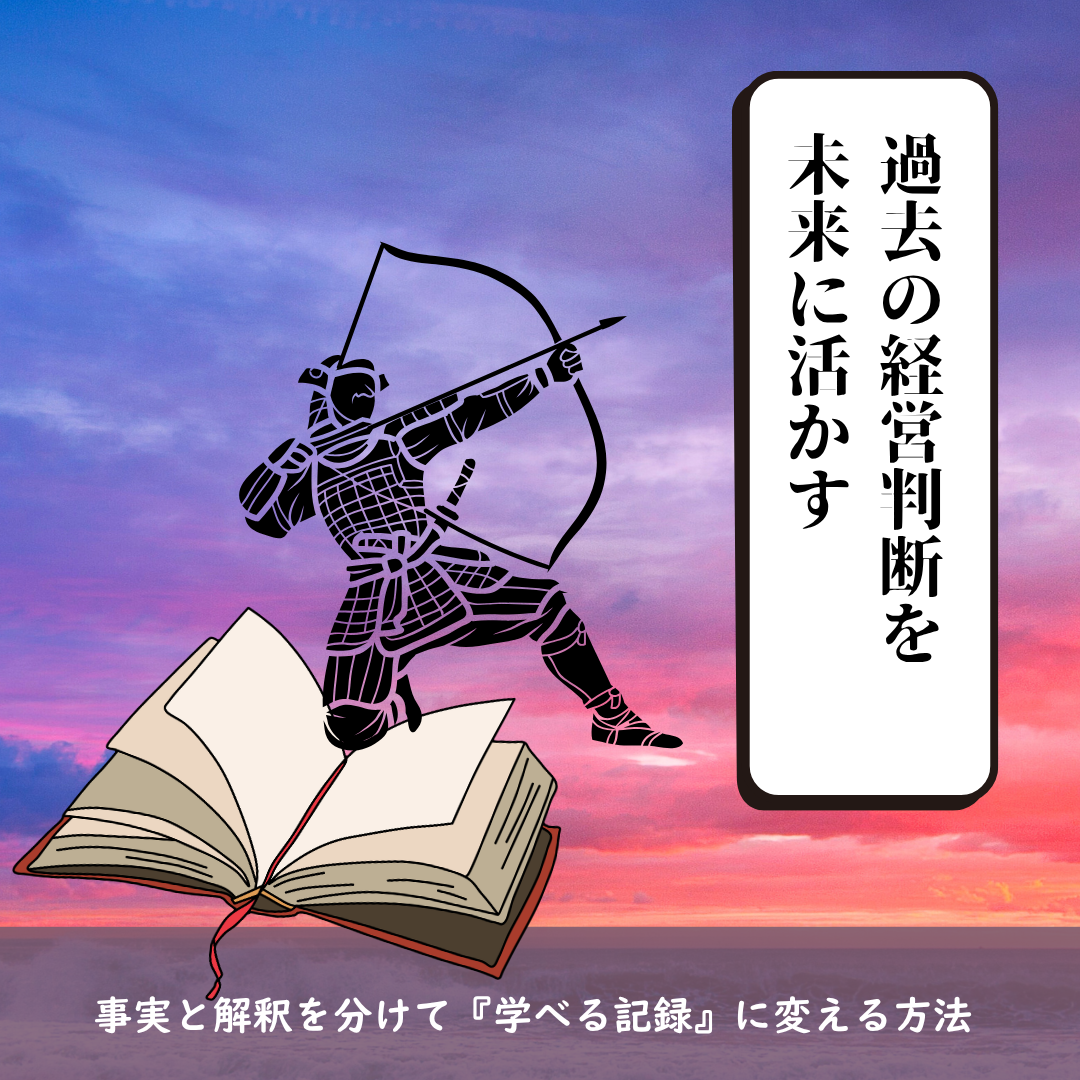
今週読み終えたのは直木賞作家今村翔吾さんの「茜唄」。
本の裏表紙に「直木賞作家による、熱き血潮が巡る『真』平家物語!」とありますが、平家物語をモチーフにした歴史小説です。
主人公は平清盛の四男・平知盛。滅びゆく平家を彼の視点から描いたもので、仕事の行き帰りの電車の中で、一気に読み通した感じです。
日本史では、平清盛が亡くなって以降、平家が都落ちして、一の谷、屋島、壇ノ浦と源氏に三連敗して、最後は滅亡したと習います。それは、史実としては正しいのですが、小説を読むと
・平家も盛り返せる可能性があったのではないか
・もし、状況が少しでも違っていたら、違った結果になっていたかもしれない
と思わせます。
もちろん小説ですから、多少のフィクションは盛り込まれているかと思います。けれども、我々は、過去の事実に対して、結果を知っているので、途中の経過については、どうしても最終結果から解釈しがちです。
つまり、「戦略Aではなく、戦略Bを採用していれば、あの戦いも勝てたのではないか」と考える傾向があります。
しかしながら、当事者としては、「いろいろなやり方はあるけれど、やはり今は戦略Aがベストの選択だ」と決断して、行動に移します。
「茜唄」の中でも知盛始め、平家の武将たちは、勝つために知恵を絞り、戦略を立てて、戦に臨みます。「これなら勝てる」「最悪でもこれなら負けない」と考えて戦う訳ですが、時の流れや様々な要因が重なって、結果的には負けてしまいます。
特に歴史の場合は、勝者が歴史の物語を作るので、どうしても、敗者は悪者にされがちです。平家もそうですが、関ヶ原の戦いで敗れた石田三成もしかり、そして、明治維新の際の徳川幕府しかり、です。
一方、最近では研究が進んで、石田三成や幕末の徳川幕府の幕臣たちを再評価する動きもありますが、私たちは、歴史を始めとする過去から学ぶ際には、
- 事実
- 解釈
を明確に分けて知ることで、より良い教えを得られます。
これを会社経営に活かすとしたら、節目となるような出来事に対して
客観的な事実と主観的な解釈を区分して記録を残す
です。
例えば、1億円を銀行から借りて、新たに工場の設備を増設する場合。
事前に事業計画を立てて、「これなら1年半で設備投資資金を回収できる」と考えても、その通り上手くいくケースもあれば、必ずしも、計画通りには進まないケースもあります。
この場合、計画を立てる段階において、客観的な事実として、「今後はこの市場は3倍に伸びる」というデータがあっても、それをどのように解釈するかは、人によって違います。また、同じ人でも、タイミングが違うと同じデータに対する解釈も変わってきます。
知人のある経営者は株式投資をやっておられるのですが、ある時から売り買いのタイミングで、その時の自分の気持ちや感情も記録し始めました。
相場の読みが当たっている時は株価の変動に対しても冷静でいられます。けれども、相場の読みが外れて、含み損が出ている時などは、どうしても損を取り返そうとしがちです。でも、これは頭では分かっていても、いざ、そのような場面になると、冷静にはなれません。
このため、その経営者の方は、記録を取って、その時の気持ちも含めて過去を振り返ることで、より冷静に判断ができるようになったそうです。
実は前述の小説「茜唄」の中でも、記録を残すことが、物語全体の大きな骨子になっています。
結果が出てからでは、どうしても、結果に引っ張られた解釈となります。会社として、何かしら大きな決断をされる際には、そのプロセスにおいて
客観的な事実と主観的な解釈を区分して記録を残す
ことで、最終的な結果如何に関わらず、過去をより活かすことができます。
追伸
来週はお盆休みという方も多いかと思います。「茜唄」は文庫本で読めますので、ご一読をお勧めします。
★関連する記事は
↓ ↓ ↓
「失敗に固執してあっさり諦めるのは成長が止まる会社、成果に固執してしつこく粘るのが成長し続ける会社」です。
ヒーズでは、弊社の日頃の活動内容や基本的な考え方をご理解いただくために、専門コラム「知恵の和ノート」を毎週1回更新しており、その内容等を無料メールマガジンとして、お届けしています。
上記のフォームにご登録いただければ、最新発行分より弊社のメールマガジンをお送りさせていただきます。お気軽にご登録いただければ幸いです。