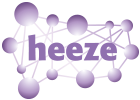ミセルチカラの磨き方
答えに詰まる質問ほど、相手の成長を引き出す
心意気を形にするコトノハ職人、岩井洋美です。
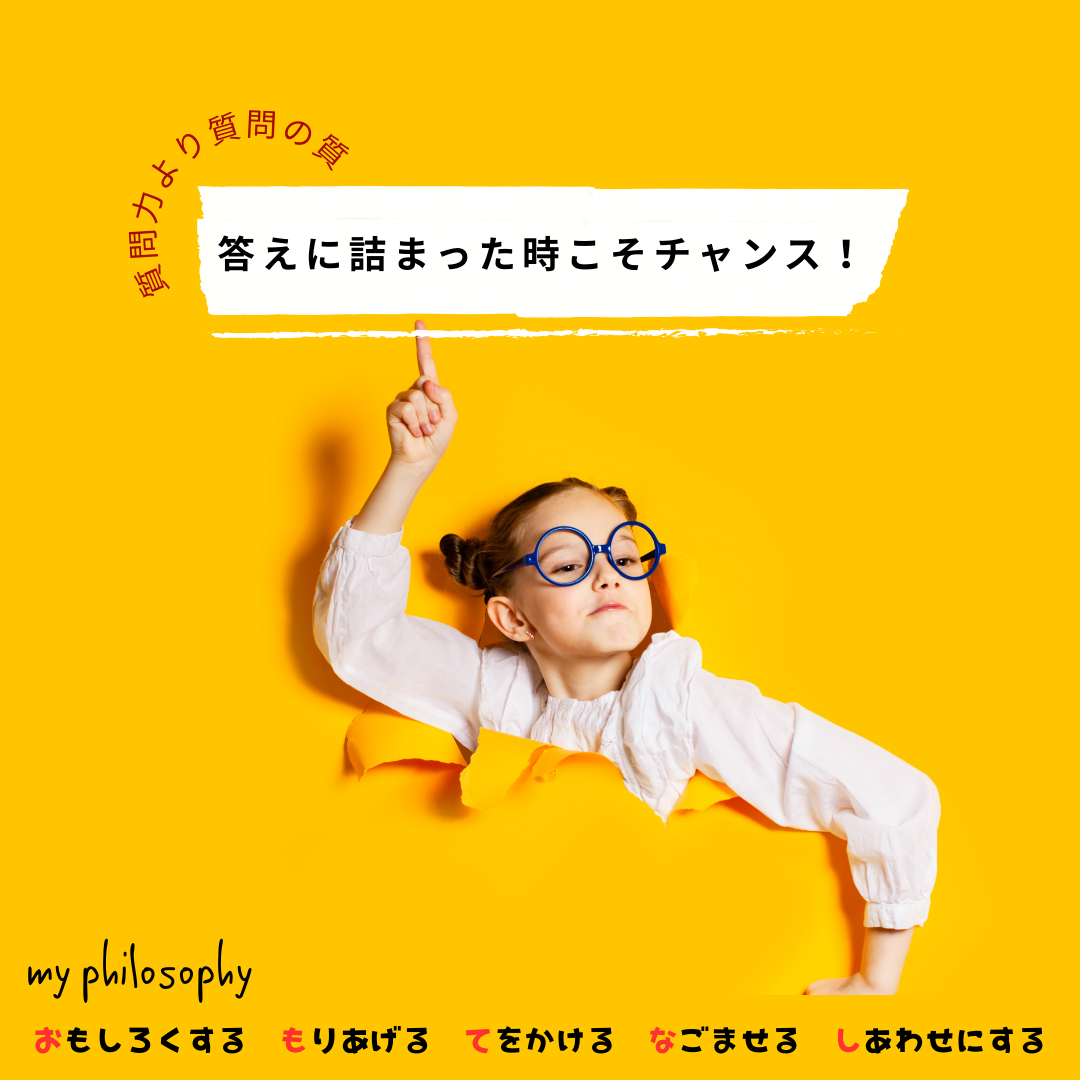
今週放送されたNHKで放送中の「プロフェショナル仕事の流儀」をご覧になった方もいらっしゃるでしょうか。フレンチのシェフ小林圭さんを密着していました。
お客様にお出しする料理の最後の味を決めるタイミングで、番組スタッフがシェフに質問をする場面がありました。
シェフにとって最も大事な時の声かけに、シェフはすかさず一喝。それは当然のことだと思います。
さらに私は、「質問」そのものにも疑問符がつきました。
その時に限らず、番組スタッフのシェフへの質問は実に「浅い」ものばかりだったからです。
「質問力」という言葉もあります。「質問」の技術についての本もたくさんありますし、「質問」の種類は、ちょっと知っている人なら、クローズドクエスチョンとオープンクエスチョンがあると分かります。
「イエス/ノー」で答えられる質問ではなく、相手が自由に考えて答えられる質問をすることが大事とも言われますから、シチュエーション別の質問集のようなものも山ほどあります。
もちろん、知識として知っておくことは無駄ではありませんが、知っていることと実践で使うことはまた別問題。実践になったときには、想定通りになんかいかないからです。
「言われたとおりに質問したのに、うまく相手の考えを引き出せなかった」
ということはないでしょうか?
想定通りにならなかったときに焦るのは、「質問の仕方」という手段に頼っているからに他なりません。
質問の種類や、質問文よりも、こだわりたいのは質問の「質」です。たとえ相手が考えて答えるような質問をしたとしても、浅い質問をしていては何の変化も起こりません。そして、相手には満足感も残りません。
では、浅い質問か深い質問かの見極めはどこでするのか?
相手の反応です。
質問をした相手が、そのことを考えてスラスラと答えたとします。とても良い反応であるときほど、それに流されないことも必要です。その答えはいつも考えていることかもしれませんし、その人にとっての当たり前のことかもしれないからです。
逆に、相手が答えに詰まってしまう質問ほど大事だということ。つまりそれは、今まで自分が考えたこともない視点からの質問だったり、考えたくなかった本質をついたことだったりするからです。
もちろん、相手を追い詰めるとか、困らせるということではありません。その人の常識や当たり前から離れた角度で、いかに切り込んだ質問を投げかけられるかということです。
よく「質問で相手に気づきを与える」と言われますが、それは質の高い「深い質問」ができてこそ可能になると思っています。これまでに学んだ「こういう場合にはこういう質問をする」をなぞるうちは、浅い質問を繰り返すことで終わってしまう可能性もあります。
深い質問をすることが目的ではなく、相手の反応をよく見て、視点を変えていくことができたら、結果的に何らかの気づきが生まれたり、満足感や安心感につながったりするということです。
浅い質問は相手の当たり前をなぞるだけ。深い質問は常識を揺さぶり、新たな視点を届けます。
「プロフェショナル仕事の流儀」のスタッフの人にもこういうことを知ってて欲しいな~と思ってしまいました。
…まぁそれは、大きなお世話なんですけれど。
それでは、今日も1日お元気で。
★関連する記事は
↓ ↓ ↓
お客様の「本音」を聞いたら、新事業のヒントが見えた
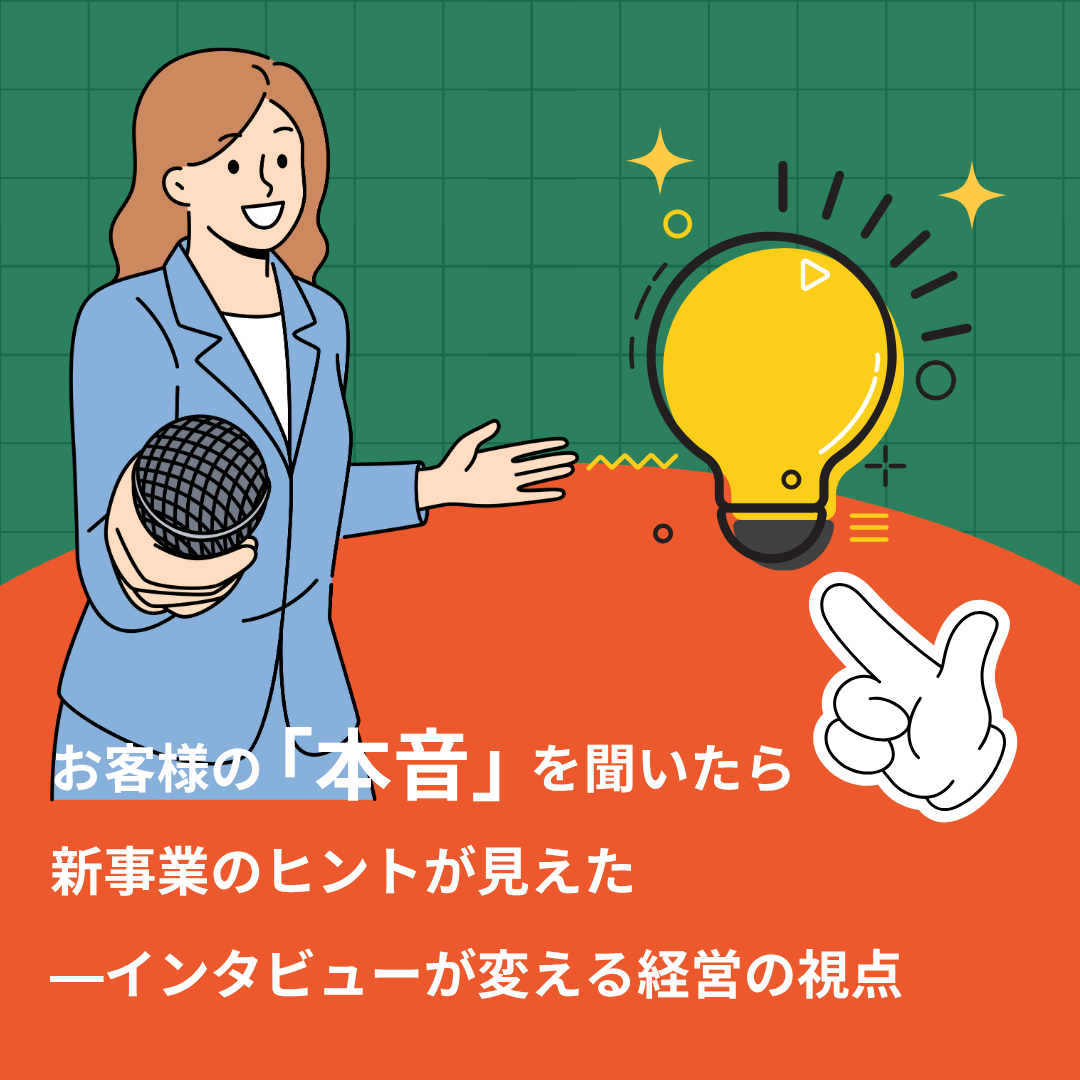
もし、今までお客様に「なぜ、ウチから買ってくれるのか?」を聞いたことがなかったら、ぜひ一度何人かにインタビューしましょう。複数の人の回答に共通する項目があったら、それが「コア・バリュー」を見つけるためのヒントになります。
ヒーズでは、弊社の日頃の活動内容や基本的な考え方をご理解いただくために、専門コラム「知恵の和ノート」を毎週1回更新しており、その内容等を無料メールマガジンとして、お届けしています。
上記のフォームにご登録いただければ、最新発行分より弊社のメールマガジンをお送りさせていただきます。お気軽にご登録いただければ幸いです。