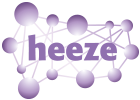ミセルチカラの磨き方
「自分は教えるのが下手」─その気づきが組織を強くする。人材育成で迷った時の分岐点
ヒーズ株式会社の岩井徹朗です。
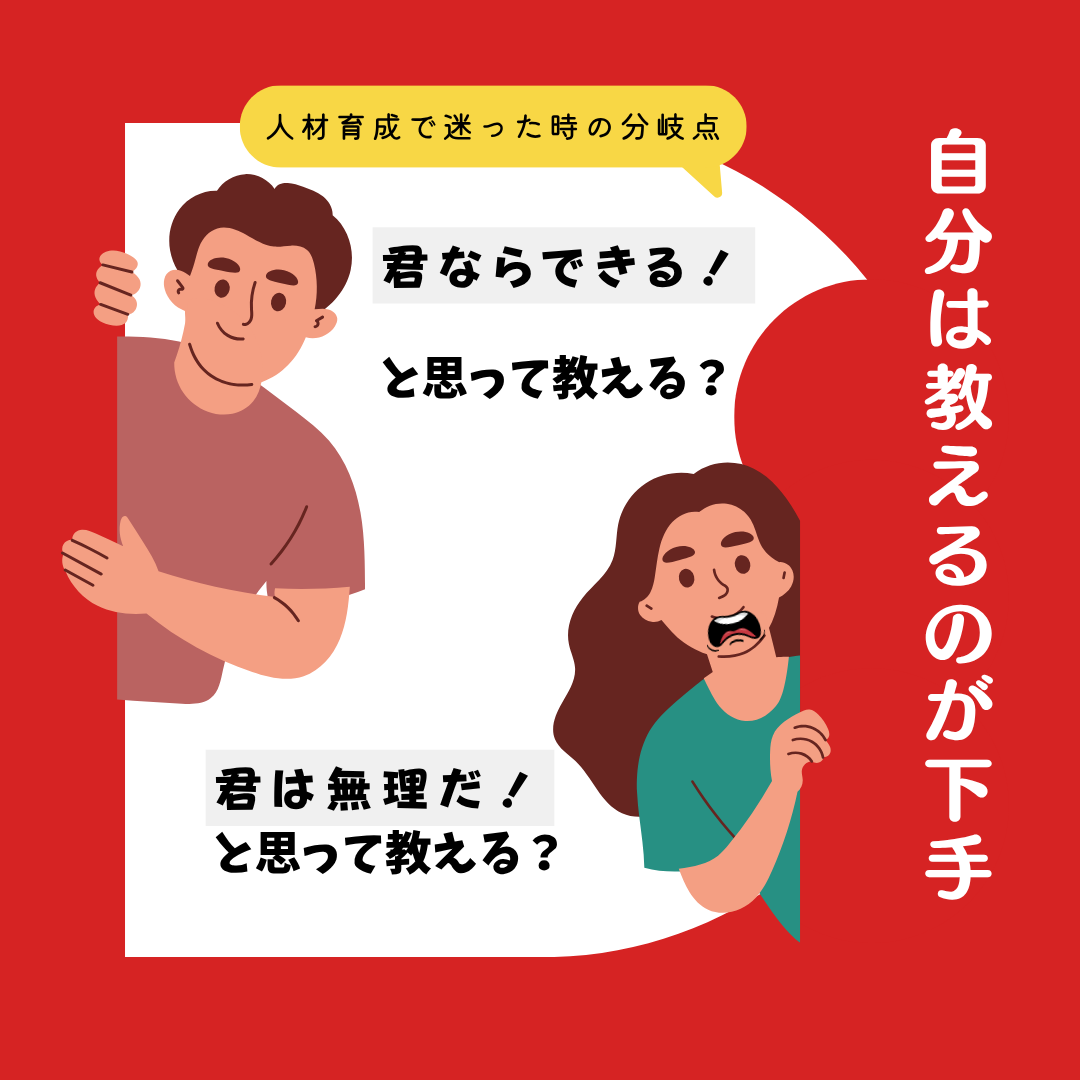
「君ならできる」と思って教えるか、「君は無理だ」と思って教えるか。
当たり前ですが、前者の方が相手は頑張ります。
しかしなら、最初は「君ならできる」と思って指導していても、
・何度教えても同じようなミスを繰り返す
・自分の殻にこもったままで、行動を変えようとしない
ことが続くと、「これ以上教えても無理」と感じることも少なくありません。
何かしらの提案をして
「ウチの社員には無理です」
といった発言があった際、経営者に
「では、社員の可能性を信じていないのですか?」
と質問すると、
「いえ、そんなことはありません」
という回答がたいてい返ってきます。
しかしながら、過去にいろいろと取り組んだことを挙げて
「本当はやって欲しいと思っているけれど、難しいと思う」
といった流れになるのです。
この場合、「自分では(社員を)上手く育てられない」と自己認識しているなら、改善する方法はあります。
経営者でも、自分で売上を上げるのは得意だけれど、そのやり方やコツを人に教えるのは苦手という方がおられます。
「名選手必ずしも名監督ならず」と言われるように、自分でできることと、それを人に教えることは、別問題です。
もし、社員を育てることが苦手なら、
・教えるのが得意な社員に任せる
・社内に適任者がいなければ、外部のリソースを活用する
ことで解決できる可能性があります。
より厄介なのは、「自分では(社員を)上手く育てられない」と自覚せずに、「あの社員には教えても無駄だから」と決めつけているケース。
人材育成が上手くいくのは
「君ならできる」と思って教える
→教えて上手くいかなくても、教える側が「どうやったらできるようになるか」を常に考えて仕掛けを続ける
→社員も少しずつでもできるようになる
です。
一方、人材育成が上手くいかないのは
「君ならできる」と思って教える
→教えて上手くいかないと、諦めて「これ以上は無理」と感じて、仕掛けるのを止める
→社員はできないままに止まる
です。
自分は「教えるのは無理だ」と深層心理で感じている人が、第三者である社員に対して「君ならできる」と思うことは難しいです。つまり、自分の可能性を否定している人が、人の可能性を信じることはできません。無理の連鎖が生まれて、組織としての成長を止めることになります。
また、「こんな自分でもできたのだから、社員もできるはずだ」と時々おっしゃる経営者がおられます。しかしながら、「こんな自分でもできた」という方は、それが故に経営者になっておられるのであって、同じことを社員に期待しても上手くいきません。
できなかったことを、何がきっかけとなり、どのようなプロセスを経て、できるようになったのかを言語化できれば、それを体系化することで、同じようにできる社員を育てることができます。
けれども、そのような言語化や体系化なしで、「自分でもできたのだから」という理屈だけでは人に行動変容を促すことはできないのです。
「こんな自分でもできたのだから、社員もできるはずだ」は社員に対する相手に対する期待。一方、「君ならできる」と思って、教え続けるのは、相手を信じていることです。
人に期待している時、その人が期待にそぐわない結果になると、「あいつはダメだ」という評価につながります。
もし、「こんなにいろいろとやっているのに、一向に成長しない」と社員に不満を感じておられるなら、まずは
- 自分は社員の可能性を本当に信じているのか
を自問自答してみましょう。
もし、その答えがY E Sなら、
- 創意工夫を重ねて育てる仕掛けをやり続ける
しかありません。その際、経営者が自らやるのか、他の社員や外部の力を活用するのかは、やり方の問題です。
逆に、答えがN Oなら、その人は人材育成に下手に携わらない方がベター。
最悪なのは、「自分は教えるのは無理だ」と認識せずに、社員に対しては、「どうせ教えても無理だ」と決めつけていること。
少なくとも、「自分は教えるのは無理だ」と自己認識できたら、無理の連鎖を断ち切ることは必ずできます。
★関連する記事は
↓ ↓ ↓
「考えない社員」は存在しない|原因を特定できたら、考える人材は必ず生まれる

「もっと考えろ」だけでは育たない。教えるべきは方法と基準。恐れを解き、視点を促せば、自走する人材は育ちます。
ヒーズでは、弊社の日頃の活動内容や基本的な考え方をご理解いただくために、専門コラム「知恵の和ノート」を毎週1回更新しており、その内容等を無料メールマガジンとして、お届けしています。
上記のフォームにご登録いただければ、最新発行分より弊社のメールマガジンをお送りさせていただきます。お気軽にご登録いただければ幸いです。