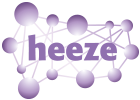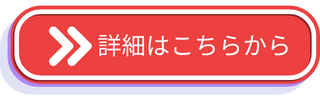ミセルチカラの磨き方
「262の法則」は無視せず活かす:組織を壊さずに改革を進める視点とは?
ヒーズ株式会社の岩井徹朗です。

組織のマネジメントでよく使われる「262の法則」。
どのような組織においても
- 貢献度の高い優秀な人が2割
- 普通の人が6割
- 貢献度が低く優秀でない人が2割
になるという法則です。
そして、「だったら、下の2割の人を排除したら良いのでは」となりそうですが、実際には「下の2割の人が辞めても、新たに下の2割になる人が出てくる」とも言われています。
先日ご相談のあった案件も「まさにこれって『262の法則』に当てはまるかも」と思えるものでした。
勤務態度の悪い社員が最終的に会社を辞めてほっとしていたのに、今までまじめに仕事に取り組んでいた社員の中で、新たに問題が発生したのです。
経営者からすれば、「今まではよくやってくれていたのに、なぜ?」と思いもあり、ご相談がありました。
いわゆる「法則」の中にはニュートンが発見した「万有引力の法則」のように、科学的にもその正しさが証明されているものもあります。
一方、「〇〇の法則」といっても、自分の経験や知見をもとに「AだからBだ」と主張されている法則も数多くあります。
そういう意味では、前述の「262の法則」はいわゆる経験則であり、必ずしも、絶対的に正しい法則とは言えないかもしれません。しかしながら、ある程度汎用性の高い「法則」はそれを無理やり変えようとするのではなく、その「法則」を前提に対策を立てた方が実務的には解決が早いです。
つまり、先のご相談の事例で言えば
- 新たに下の2割になってしまった社員を元の6割に戻そうと頑張る
- 新たに下の2割になってしまったという前提で、必要な手を打つ
なら、後者の方をお勧めします。
特に会社が更なる飛躍のために経営改革を進めていると、今まで普通に働いていた6割の社員の中にも、不満や不平を抱く人が出てきます。
そのプロセスの中で、下の2割が会社のやり方についていけずに辞めてしまうのは想定内ですが、6割の中から下の2割になってしまう人が出てくるのも仕方がないと割り切った方が改革は進みます。
「法則」に逆らって、下の2割になってしまった人と個別面談したり、待遇を改善したりして、なんとか元の6割に戻そうと努力してもなかなか上手くいきません。
それよりも、社員が新たに下の2割になってしまうのは法則上やむを得ないことを前提にして、
- その社員の仕事の進捗管理をより厳密にする
- その社員が不正を起こさないように注意する
- その社員が他の社員に悪影響を及ぼさないよう対策を立てる
方が会社にとっては有効です。
人手不足が続く中、それまでまじめに働いていた社員の言動が変わってしまうのは、経営者としても頭が痛いところです。
その際、あえて法則を無視して、そこにエネルギーを使うのか、それとも法則を参考にして、別な視点から経営資源を配分するのか。
経営者は「Cool Head & Warm Heart」が必要と言われていますが、時にはやさしさが甘さにつながって痛い目にあうので、汎用性の高い法則には冷静な頭で向き合いましょう。
なお、ご自身の「構造」を知ることは、自分が無意識の中で従っている法則を理解することにもつながります。詳しくは「こちら」をご覧ください。
↓ ↓ ↓
★関連する記事は
↓ ↓ ↓
「最善も最悪も滅多に起きない」現実を踏まえた経営判断のすすめ
最善も最悪も滅多に起きない。希望と恐怖の間で、冷静に一歩を踏み出す判断力が経営を安定させます。
ヒーズでは、弊社の日頃の活動内容や基本的な考え方をご理解いただくために、専門コラム「知恵の和ノート」を毎週1回更新しており、その内容等を無料メールマガジンとして、お届けしています。
上記のフォームにご登録いただければ、最新発行分より弊社のメールマガジンをお送りさせていただきます。お気軽にご登録いただければ幸いです。