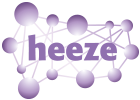ミセルチカラの磨き方
経営の現場に必要なのは「問いを持ち続ける力」
心意気を形にするコトノハ職人、岩井洋美です。
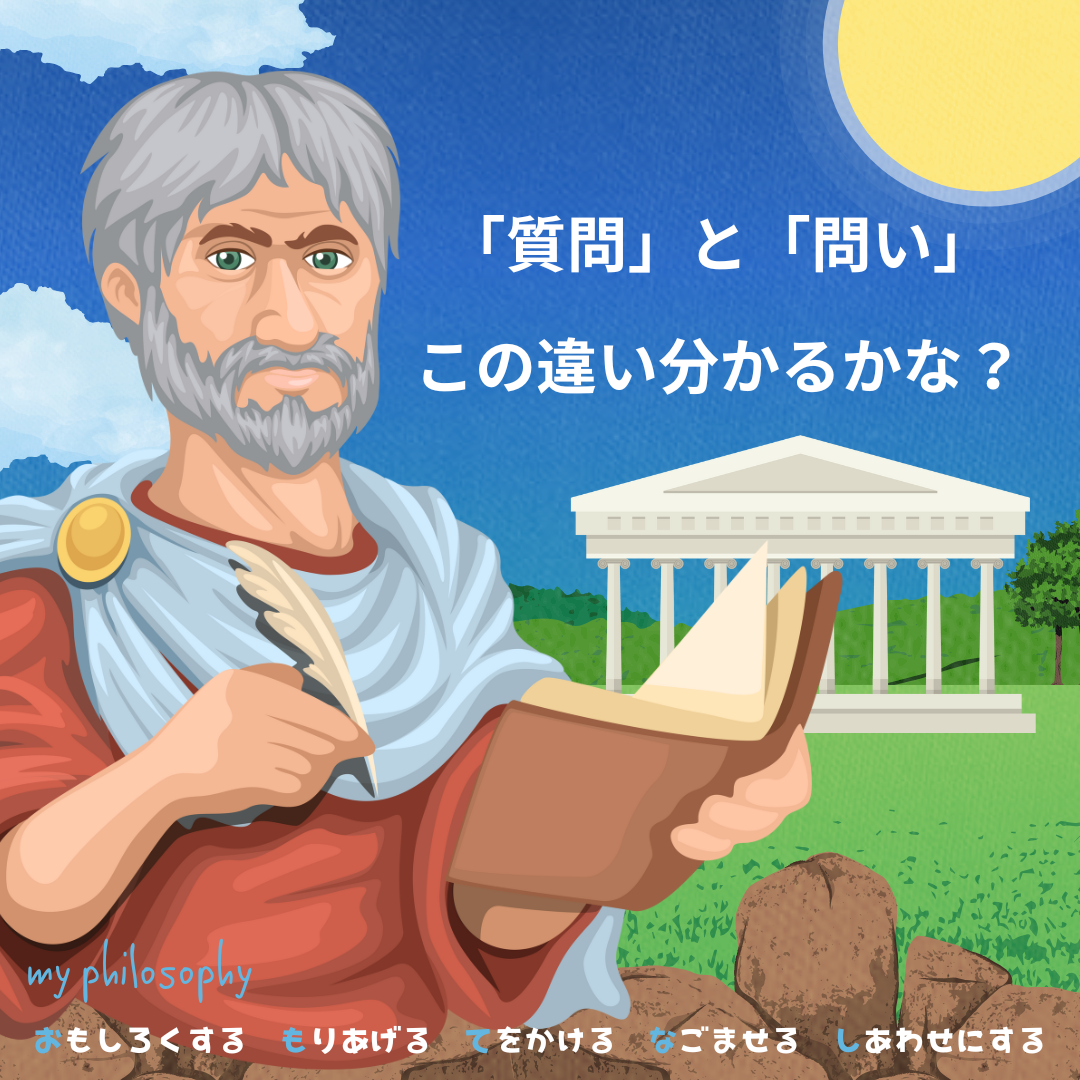
猛暑続きの時は「もうちょっと涼しいといいのに」と言っていましたが、こう気温が下がってくると「こんなに寒くなくていい」と口にしているんですから、勝手なものです。
急な気温の変化ですから、体調の管理には気をつけたいところですね。
さて、1ヵ月前くらいにも「答えに詰まる質問ほど、相手の成長を引き出す」っていうことをお伝えしました。
自分が言ったことに間違いはありませんけれど、相手が答えに詰まるような質問をしようと思ったら、「質問」というものに対するイメージや認識を変えないといけないということに気づかされることがありました。
それは、「一問一答」という捉え方です。
「これはいつまでにできる?」
「あれはどこまで進んでるの?」
「誰がやることになったの?」
「そのことをどう考えてるの?」
「それを優先してやる理由は何?」
「その問題の原因は何?」
日常業務の中での「質問」はいろいろ考えられますが、多くは確認したり、考えを聞いたりするものです。情報を得るためのツールという考え方もできます。
中には答えに詰まるような質問があったとしても、「一問一答」を繰り返すことで成り立ちます。
この場合、答える側には、答えがあります。そして、質問する側にも、「こう答えてほしい」という「期待を込めた答え」や「こう答えるんじゃないか」という「予測した答え」があったりもします。
また、相手に深く考えさせて答えを導くための質問を「発問」という言い方もしますが、これも基本的に質問する側に導きたい「意図」があります。
質問にしろ、発問にしろ、どちらであっても、情報や答えを得ることが目的だとしたら、「問い」は意味や気づきを深めることが目的です。
そして、質問者は「問い」の答えを持っていません。「問い」の答えは、答える側の中にあるものだからです。
例えば、社長が社員に
「お客様との信頼が薄れているとき、どう修復しているか?」
と質問したとします。
ここには、その人がやっていることがあるはずですから答えがあります。
でもそれを聞いただけでは、この人がなぜそうするかは分かりません。
その質問で方法だけを聞いて終わってしまったら、そこに潜んでいるその人の大事にしている想いにはたどり着かない。そこにある大事な理由まで分かった上での修復方法なら、その会社のロールモデルにだってなります。
- 質問は「知っていることを聞く」
- 発問は「知らないことを考えさせる」
- 問いは「自分の中に“まだ名づけられていない何か”を掘り起こす」
多くの人は、「答える=評価される」経験を積み重ねてきています。
学校でも職場でも、「正しい答えを言う」ことが求められてきました。だから、質問に対しては、「考える」ではなく「当てにいく」になってしまいます。
そういう人が質問をする側になったときには、結局、答えを求めますから、一問一答になるということです。
経営の現場では、「問い」がなければ思考が止まります。
目の前の問題を解くための質問も必要ですが、自分たちがどんな未来をつくりたいのかを考える「問い」がなければ、組織はいつしか作業で回るだけになってしまう。
「問い」は、相手を試すためのものではなく、相手と一緒に「見えない答え」を探していく道筋。そして、その道筋の中で、自分の心意気もまた育っていくのだと思います。
答えを出すことに慣れた人ほど、「問い」を持ち続ける力を。
今日もひとつ、自分に「問い」を持って過ごしてみてください。
それでは、今日も1日お元気で。
★関連する記事は
↓ ↓ ↓
答えに詰まる質問ほど、相手の成長を引き出す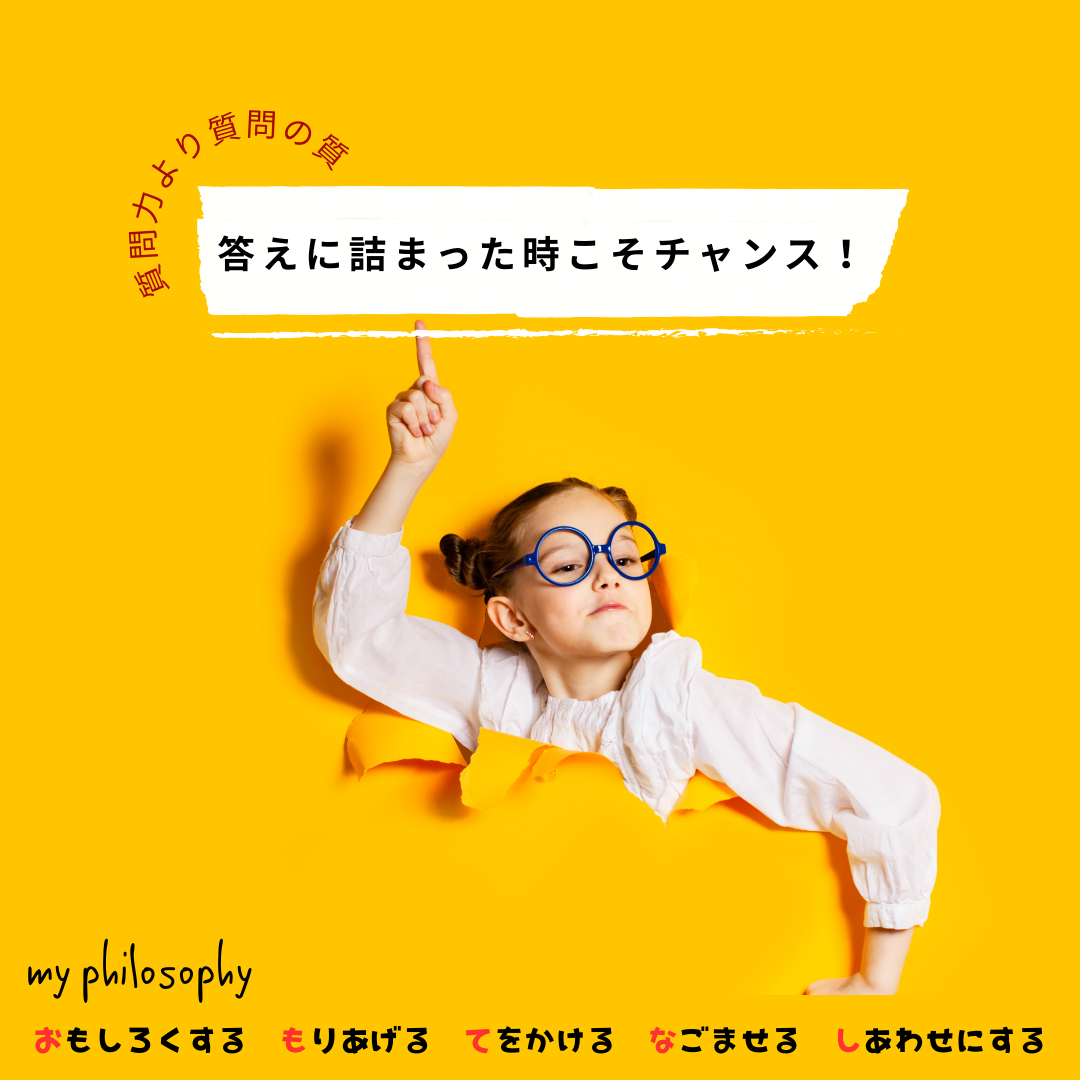
浅い質問は相手の当たり前をなぞるだけ。深い質問は常識を揺さぶり、新たな視点を届けます。浅い質問は相手の当たり前をなぞるだけ。深い質問は常識を揺さぶり、新たな視点を届けます。
ヒーズでは、弊社の日頃の活動内容や基本的な考え方をご理解いただくために、専門コラム「知恵の和ノート」を毎週1回更新しており、その内容等を無料メールマガジンとして、お届けしています。
上記のフォームにご登録いただければ、最新発行分より弊社のメールマガジンをお送りさせていただきます。お気軽にご登録いただければ幸いです。