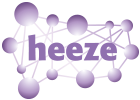知恵の和ノート
「申し訳ありません」が逆効果?謝罪が炎上を招く時代の経営術(第608話)
社員の言葉の奥にある心の声が顧客の信頼を左右する。小さな問題が起きた時も原因を深掘りして、誠意ある対応のベースを築こう。

以前脳科学に詳しい先生に教えていただいたのですが、音声を伴う外言と音声を伴わない内言を比べてみると、人間の脳は外言よりも内言の方により反応するそうです。
つまり、声に出して「ありがとう」と伝えるより、心の中で「ありがとう」と唱える方が相手にはより感謝の気持ちが伝わります。これは逆に考えると、「申し訳ありません」と口では言っても、心の中で「うるせぇ、バカ!」と思っていたら後者の方が伝わることになります(笑)。
大きなトラブルが起こって企業のトップが謝罪会見をする際、「申し訳ありませんでした」と深々と頭を下げていても、「この人、本当は『自分のせいじゃないのに』と思っているだろうなぁ」と感じることが多いのは、脳が前述の内言に反応しているからかもしれませんね。
最近はカスタマーハラスメントが問題となっています。このため、ちょっとしたトラブルに対しても、「社長を出せ!」と過剰なクレームをつけてくる人がいるのは事実です。
一方、最初は小さな問題であっても、会社の対応が表面的であるがために、やがて大きなトラブルに発展するケースもあります。
あるクライアントさんでも、ちょっとした情報の行き違いで、危うく大きな問題になりそうなケースがありました。
昨今は自社だけですべてを完結するのではなく、外注先や委託先と協力しながら仕事を進める会社も多いかと思います。けれども、お客様からすれば、契約した先がA社であったら、問題を起こしたのがA社の社員であろうが、委託先のB社の社員であろうが、関係ありません。
その際、お客様から苦情を受付けたA社の社員が「それはウチの社員じゃなくて、B社の社員がやったことなのに」と心の中で思いながら対応していると、ちょっとした言動の中で、「この人はこの問題に対して無関心なのではないか」とお客様に感じさせる恐れもあります。
そうなると、
委託先のB社の社員が起こした不手際×契約元のA社の社員の不誠実な対応
となって、最後は会社のトップである社長が謝罪に行かざるを得ないことにもなります。
幸いクライアントさんの場合には、社長が「お客様にはこういうふうに伝えといて」と社員に指示したので、お客様も納得され、大きな問題にはなりませんでした。
大きなトラブルが発生する際、その要因は必ず複数あります。つまり、一つの小さなミスではなく、いくつかの小さなミスが重なって大きなトラブルになります。
そして、小さなミスが重なる際の背景には
・人に仕事が張り付いている
・仕事が特定の人に集中している
・社員の入れ替わりが激しい
・立派な経営理念がお飾りになっている
・社内ルールが一部の社員にしか浸透していない
・上司が部下に仕事を丸投げしている
・社員を育てられる人材が社内にいない
・問題が起きても原因を分析していない
・問題が起きても改善策を立てずに放置している
・過去に起こった問題を社内で共有していない etc.
といった問題があります。
組織としてしっかり対応するには、その場しのぎの対策ではダメ。もし、トラブルが発生するたびに経営者が毎回謝罪に駆けずり回っているようでは、本来の仕事に支障をきたします。
「1件の重大事故の裏には29件の軽微な事故と300件の怪我に至らない事故がある」と言われています。そして、表面的な対応だけでなく、トラブル時ににじみ出る「心の声」まで整えるには、それなりの時間がかかります。
怪我には至らない小さなトラブルが起きた時に、「この問題の背景にはどのような問題あるか」を考えて、必要な対策を早め早めに打っていきましょう。
★「仕事の見える化」や「人の見える化」で第三者の力が必要な際には「こちら」がお役に立ちます。
↓ ↓ ↓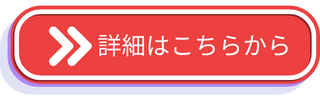
★関連する記事は
↓ ↓ ↓
社員の軽いルール違反が会社を壊す
小さな違反を見逃す甘さが、会社の信頼を崩す。情に流されない判断が会社を守ります。
ヒーズでは、弊社の日頃の活動内容や基本的な考え方をご理解いただくために、専門コラム「知恵の和ノート」を毎週1回更新しており、その内容等を無料メールマガジンとして、お届けしています。
上記のフォームにご登録いただければ、最新発行分より弊社のメールマガジンをお送りさせていただきます。お気軽にご登録いただければ幸いです。