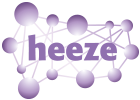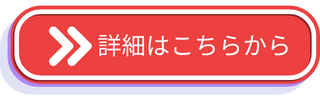知恵の和ノート
「避けたいこと」にこそ経営のヒントがある:曖昧な目標からの脱出法(第596話)
「絶対に避けたいこと」を言語化せよ。そこにこそ、あなたオリジナルの経営判断の軸と、ぶれない意思決定が生まれる。

「何を目指しているか」という質問の他に、「何を避けたいか」と経営者にお伺いすることがあります。
その場合、前者の回答がかなりふわっとしている場合でも、後者の回答はより具体的なケースが多いです。
例えば、避けたいことが「借入はしたくない」という場合。
「これまで無借金経営を続けてきたので、たとえ銀行からでも借入したくない」
という回答もあれば
・銀行借入なら良いが、ノンバンクはから借入したくない
・自宅を担保に入れてまで借入したくない
・A銀行なら良いが、B銀行には頭を下げたくない
など、様々です。
ただし、これらの回答はまだ表面的なもの。経営者の本音に迫るためには、さらに突っ込んでいく必要があります。
そして、「自宅を担保に入れてまでは借入したくない」というケースでは、「家族に迷惑を掛ける」ことが絶対に避けたいことであれば、それをベースにして対策を考えることになります。
「何を目指しているか」という質問に対して、明確な目標が定まっているなら、「その目標を達成するには、今回はどうしたら良いと思いますか?」という問いが有効になります。
しかしながら、明確な目標がなかったり、毎回目標が変わったりするような場合は、「何を目指しているか」を掘り下げるよりは、「何を絶対に避けたいのか」を掘り下げた方がやるべきことがハッキリすることが多いです。
大谷選手のように明確な目標を掲げて、それに向けて日々努力できるなら、その方が多くの人を巻き込むことができます。このため、「明確な目標を掲げましょう」とか「より高い目標を掲げましょう」といったことが広く推奨されます。
一方、「より高い目標を」といった場合、耳障りが良く、誰もが言うような陳腐な目標になることも少なくありません。
また、どうしても、他者との比較が生まれるので、「『売上高1億を目指す』と言っても、あの経営者に比べたら、ちっちゃいよなぁ」と自己評価を下げてしまう傾向があります。
もし、ご自身がそういう傾向があると感じておられるなら、無理やり高い目標を掲げるのではなく、「自分が絶対避けたいことは何なのか」を自分に問うてみましょう。
目指す目標がどうしても同一化するのに対して、絶対避けたいことは、その人の個性がより出るのを実感しています。
前述の例で言えば、「家族に迷惑をかけたくない」ことが避けたいことであれば、その本心の奥には「なぜ、そう考えるか」という、ご本人の経験や考え方に基づく要因があります。
そして、本心の奥底にある要因にまでたどり着き、それを言語化できたら、それは「そういう嫌な思いをする人をなくしたい」という形で、オリジナルの目標にもなります。
「何を目指すのか」に関して、正解はありません。それゆえ、すぐに見つからなかったり、いま掲げている目標があまりしっくりこなかったりしても、焦る必要はありません。
一方で、「何を絶対避けたいのか」は日々ご自身の判断基準にもなるので、まずは「何を絶対に避けたいのか」を明らかにしましょう。
★自分の想いの源をハッキリさせて、会社の更なる成長に繋げていきたいとお考えの経営者の方は「こちら」をご覧ください。

自分自身の価値観に沿ったものではなく、他者や社会の価値観に従ってしまうことに気づけないことが一番の問題です。
ヒーズでは、弊社の日頃の活動内容や基本的な考え方をご理解いただくために、専門コラム「知恵の和ノート」を毎週1回更新しており、その内容等を無料メールマガジンとして、お届けしています。
上記のフォームにご登録いただければ、最新発行分より弊社のメールマガジンをお送りさせていただきます。お気軽にご登録いただければ幸いです。