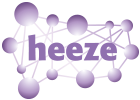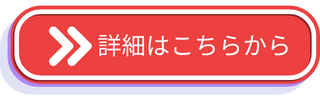知恵の和ノート
「管理職採用しても機能しない会社の共通点」─その前にやるべきこと、見落としていませんか?(第595話)
管理職が機能しないのは、仕事内容も権限も曖昧なまま丸投げするから。採用前に任せ方を言語化し、社内に徹底せよ。
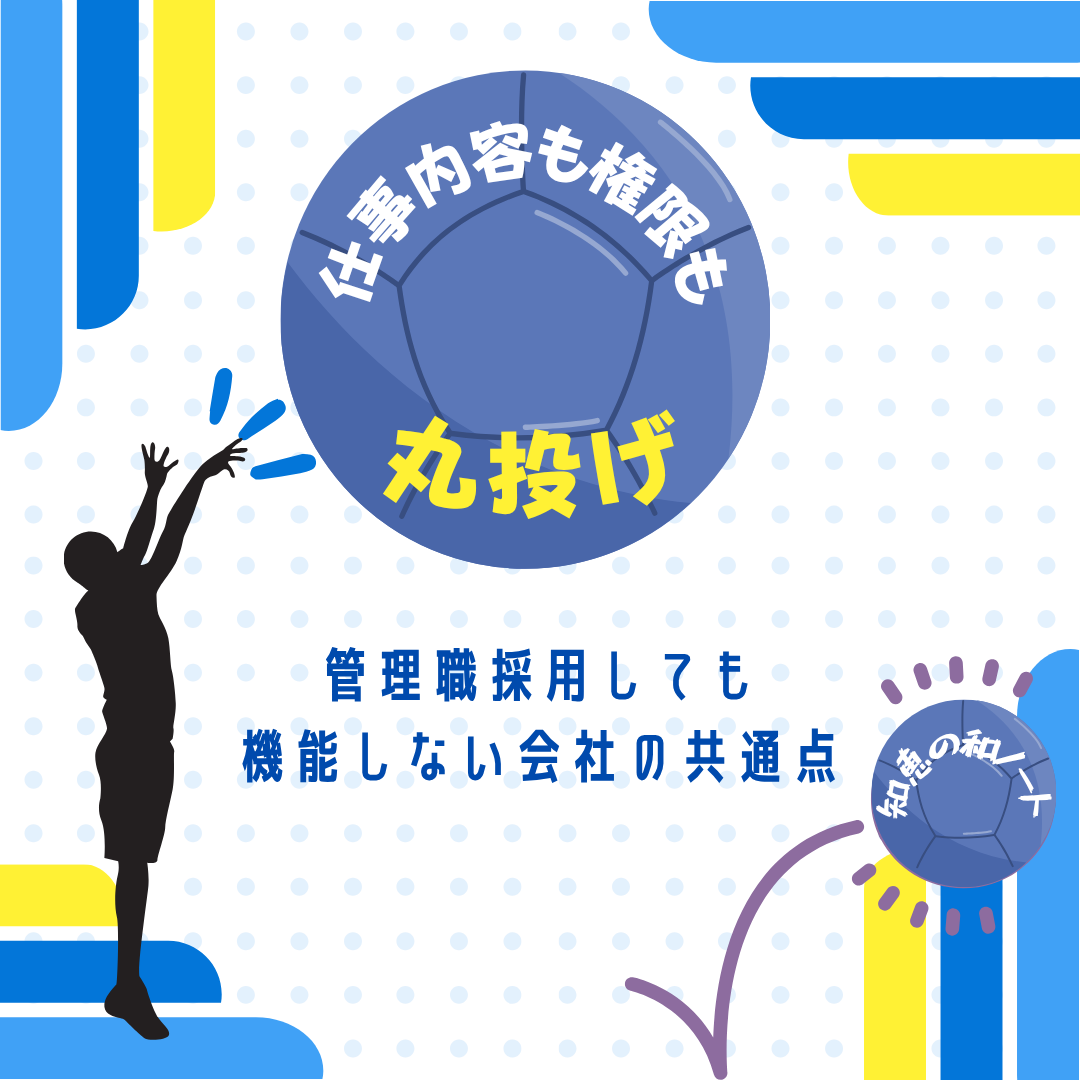
「管理職を採用したい」
・社員数が10名を超えてきた
・業績をさらに伸ばしていきたい
・けれども、いまの社員の中にリーダーシップを発揮できる人はいない
こんな状況の時、外部から人材を採用するべく、「誰か良い人はいないでしょうか?」とご相談を受けることがあります。
少人数でやっている会社の場合、経営者以外はすべて担当者で、仕事の割り振りや指導も、経営者である社長が全部担っていることが少なくありません。
そんな時、自分をサポートしてくれる管理職候補が社内にいれば良いのですが、残念ながら該当者がいないこともあります。
このようなケースで、経営者が考える「管理職」とは「経営者の意を汲んで、会社のために、自律的に働く人」です。
ただ、ざっくりとしたイメージでは、なかなか適任の人は見つかりません。
まず、「経営者の意を汲む」には、共感できる経営理念が必要ですし、会社の状況に関する情報共有も欠かせません。
次に、「会社のために」という場合、仕事の内容として、ある部門の取りまとめなのか、部下となる社員の教育や指導も含まれるのかをハッキリさせることが求められます。
そして、「自律的に働く」ためには、一定の権限を与える必要がありますし、同時に責任を負ってもらうことも不可欠です。
一方、管理職候補が社内にいない会社では
・経営理念はないか、あっても一般的内容で共感できない
・会社の財務状況などは経営者しか知らない
・仕事の内容が属人化している
・会社における人材評価の基準が曖昧
・権限は社長に集中している
・失敗したら怒られるので、社員は難しい仕事に挑戦しない
といった状況であるのが普通。
このため、仮に運よく優秀な人が採用できても、その人が会社の管理職として、経営者の期待通りの働きができるかについては、かなりハードルが高いと言わざるを得ません。
そこで、前述のようなご相談があった場合は、「良い人は簡単には見つかりません」と申し上げた後で
・やってもらいたい仕事の内容を明確に定義して社内で共有する
・たとえ、採用した人が上手く機能しなくても、会社の仕組みをつくることを意識する
・報酬についてはケチらない
ことをアドバイスしています。
仕事の内容を明確に定義して社内で共有する
実務的に自分が手を動かすことはできても、その実務を自分ではなく、別の人にやってもらって仕事が回るようにするのは、別の能力です。また、中には、手を動かさなくて、教育や指導するのが得意な人もいますが、この場合、今いる社員から「今度来た人は口ばっかりで、自分では何もやらない」と文句が出ることもあります。
このため、もし、社員の育成・管理を強化するために、管理職を採用するなら、それを本人にも伝えるだけでなく、社内でも周知徹底することがポイントになります。
会社の仕組みをつくることを意識する
前述のように理想の人はなかなかいないので、仮に採用しても、その人が途中で退職してしまうことも想定しなければなりません。
その場合、「なんだか社内を引っ掻き回されて終わった」とならないよう、少なくとも、採用前よりは会社として一歩でも仕組みが整ったと言える状況を目指すことが肝要です。
このため、採用後も丸投げするのではなく、定期的に意思疎通を図って、何が、どこまで、できているのかを必ず見える化しましょう。
報酬についてはケチらない
規模の小さな中小企業では、多額の給与を提示するのは難しいという事情は理解しています。また、頑張って他の社員より高い給与を払っても、途中で辞めてしまうリスクもあります。
けれども、確率論から言えば、より高い給与を払った方が、優秀な人が来る確率は高まるのは事実です。
いずれにせよ、社内に適任者がおらず、新たに管理職を採用する場合は、単に部長や課長を採用するのではなく、(将来的には)「自分の後継者としても良いと思える人」かどうかを一つの目安にするのがベター。
そういう意識を持って臨まないと、せっかく管理職として採用しても、部長という肩書きを持った平社員で終わるかもしれません。
★自分の想いの源をハッキリさせて、会社の更なる成長に繋げていきたいとお考えの経営者の方は「こちら」をご覧ください。
↓ ↓ ↓
★関連する記事は
↓ ↓ ↓
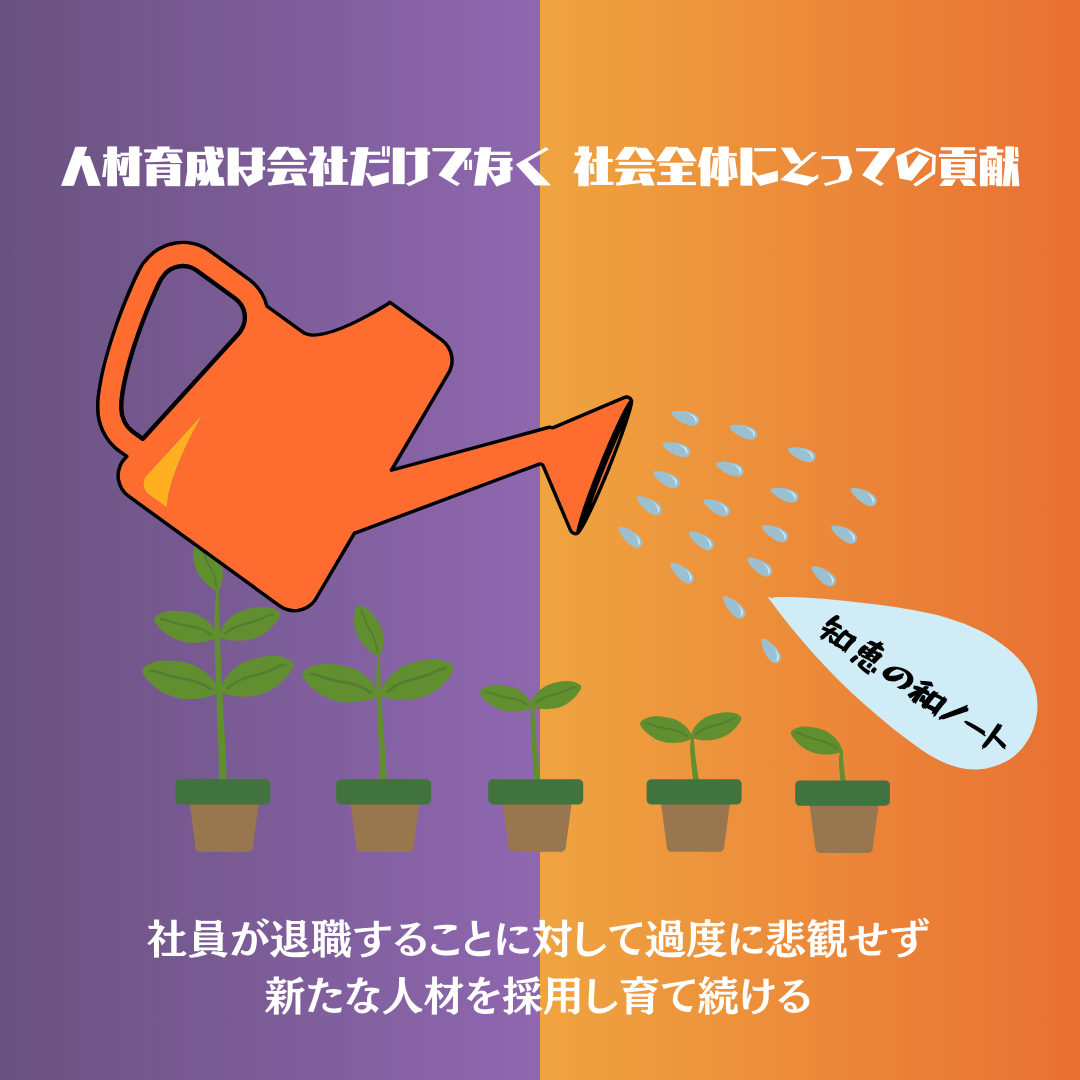
人材育成は長期的な視点を持ち、個々の社員の成長に賭け続けることが重要。たとえ、大事に育てた社員が離職しても、愚直に人材育成を積み重ねることが会社の未来を切り開く鍵となります。
ヒーズでは、弊社の日頃の活動内容や基本的な考え方をご理解いただくために、専門コラム「知恵の和ノート」を毎週1回更新しており、その内容等を無料メールマガジンとして、お届けしています。
上記のフォームにご登録いただければ、最新発行分より弊社のメールマガジンをお送りさせていただきます。お気軽にご登録いただければ幸いです。